Tipping Point Returns Vol.32 邦題が教えてくれる、日本語のややこしさと楽しさ
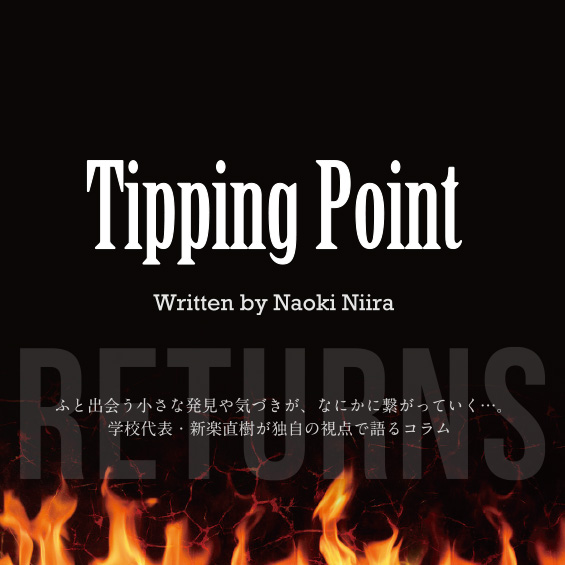
海外の人に「最もヒットした日本映画って何?」と聞かれて『劇場版 「鬼滅の刃」無限列車編』と答えられる人は多いだろう。しかしさらに「無限列車って何?」と聞かれたら説明できるだろうか? 日本映画で最も観られた作品にもかかわらず、意味はよくわからない、が答えだろう。(2025年11月時点)
「無限列車」や最新作の「無限城」も正確な意味は知らない。でも、怖さやスリリングなイメージは強く伝わってきて、とてもいい感じなのだから、それで十分では? 確かに観る側、消費する側ならそれでいいかもしれない。しかし、言葉を売る人は、それでは困る。たとえ正確な意味は伝わらなくても、時には「誤解」を誘発することになっても、「それらを意図した言葉づくりで人の心を掴む力」が求められるからだ。
私は日本映像翻訳アカデミーの映像翻訳本科で日本語を教えて30年になる。いくつかのプログラムのうち、1997年から2023年まで、総合コース・Ⅰ(旧入門コース)でも授業をもっていた。そこで題材としていたのが「洋画の邦題」だ。作品をヒットさせたい、一人でもたくさんの人に観てほしいと願う売り手は、どのような狙いで邦題を決めたのか。その理由を推察、探究することで、自分の中にも「不特定多数の視聴者・観客(市場)に響くよう、意図をもって言葉を生み出す装置」を備えることが目的の授業だ。
前課題は、今の自分の感覚で「いい感じと思う邦題とダメだなと思う邦題」を挙げ、その理由を添えること。授業では、自分の感覚は売り手の狙いを汲んだものか、市場の多数派と一致しているかを検証した。提出された前課題はいずれも興味深く、受講生と一緒にあれこれ考えて議論することは、私自身にとっても日本語強化の好機になっていた。
「無限列車」に似たケースでよく挙がったのは「ジェイソン・ボーン・シリーズ」だ。『ボーン・アイデンティティー』はまだしも、『ボーン・スプレマシー』や『ボーン・アルティメイタム』って何?日本人のほとんどはスプレマシーやアルティメイタムの意味はわからない。けど、なぜかいい感じだ。また、『プライベート・ライアン』や『ロード・オブ・ザ・リング』のケースでは、売り手は意味不明の邦題での勝負を飛び越えて、市場の「誤解・勘違い」をあえて狙ったふしがある。いずれも原題をほぼそのままカタカナにしただけですよと嘯(うそぶ)いているかのようで、実はそうではない。原題の‘Private’は単なる「二等兵」を意味するが、カタカナで「プライベート」と表記すると、一人の兵士の孤独や失意といった内面を想起させる。二等兵なんて本当の意味を知らず頭の中で誤訳されても全然OK、むしろそれが狙いなのだ。『ロード・オブ・ザ・リング』の「ロード」も同じ。原題は‘The Lord of the Rings’、つまり神や支配者のことだが、カタカナになると多くの人は「道」だと直感してしまう。しかしその誤解は「ホビットたちの長く険しい旅路」を想起させ、エモさや心地よさを醸成する。
四半世紀にわたり蓄積した提出課題には「日本語に関する膨大な調査データ」という側面もある。その結果、とても興味深い発見があった。その一つが「すべての提出課題で最も多く挙がった邦題は?」。
結論から言おう。キャメロン・ディアス主演のコメディで1999年に日本で公開された『メリーに首ったけ(原題:There’s Something About Mary)』だ。公開直後から数年間は、どのクラスでも必ずと言っていいほど複数の受講生がこれを選んでいた。その後もひたすら選ばれ続けた邦題である。
なぜ選ばれ続けたのか?「首ったけ」という言葉が原因であることは明らかだ。今でも気になる邦題を尋ねられたら「メリーに首ったけ」と答える人はいるだろう。でも、数が多いというだけでは大きな発見にはならない。問題は、それが「いい感じ」として挙げられたのか「ダメだな」と思われたのかである。
今、(えっ? いい感じのタイトルに決まってるよね?)と思った人は、きっと驚くだろう。実は、1999年から8年ほどの期間は、すべての人が「ダメな邦題」として選んでいたのだ。一人の例外もなく「首ったけ」は古い、ダサい、口にするのも恥ずかしい、と。つまりそれが日本社会全体の暗黙知だったのである。
ところが2007年のある学期のこと。いつもの如く課題に目を通していた私は衝撃を受けた。一人の受講生が「メリーに首ったけ」をいい感じの邦題として挙げていたのだ。「首ったけ」という言葉の語感の心地よさを、そう感じるのが当たり前であるかのように解説している。その後、少しずつ「首ったけはいい感じ」と書く人が増え始め、2015年くらいにかけてはクラスの中に「好き派」と「嫌い派」が同居することも珍しくなかった。そして、2017年になると提出課題から「嫌い派」が完全に姿を消す。
つまり、「首ったけ」という言葉に対する多くの人(日本社会、市場)のイメージ(意味といってもよい)が、20年ほどの歳月を経て180度変わったのである。真逆なのだ。そのプロセスを課題のデータは刻々と記録し、証明している。おそらく日本語の学者・研究者にとっては垂涎の資料だろう(絶対に外には出さないが)。言葉の意味の変化を「流行おくれ」「ダサい」、あるいは「一周回って新しい」「レトロでエモイ」などと言って済ませることは簡単だが、それがいかなる歳月を経て、どのように変化していくのかを追ったデータは稀だろう。
今、私たちの目の前にある言葉(単なる流行言葉ではない)、はどうか。世の中でのイメージや捉えられ方、使われ方は、もしかしたら真逆の方向へ変化している最中かもしれない。JVTAの修了生・受講生、つまり言葉のプロや目指す人は、そうした変化に敏感であるのはもちろん、上手く、賢く使いこなして「さすが!」と評価されるようになってほしい。
追記
「首ったけ」についてAI(Gemini)に聞いたところ「とても魅力的、効果的な言葉。日本での『メリーに首ったけ』の成功にもつながった」みたいなことを言ってくるので、「でもね」と私の「20年変遷論」を説きました。すると、「その通りです。ご指摘ありがとうございます」と手のひら返しの回答(笑)。「首ったけという言葉が持つニュアンスや世間の評価は、時代とともに変化しています。特に、『メリーに首ったけ』が公開された1999年前後から2010年代初頭にかけては、<首ったけ=古くてダサい、照れくさい表現>という認識が強く、一部の人々からは敬遠されていた可能性が非常に高いです」だって。Geminiさん、まだ間違ってますよ、一部の人じゃなくてほぼすべての人だったんだよと教えたかったのですが、お説教はここまでにしておきました。
(了)
今回のコラムで思ったことや感想があれば、ぜひ気軽に教えてください。
☞niiraアットマークjvtacademy.com
※アットマークを@に置き換えてください。
☞JVTAのslackアカウントを持っている方はチャンネルへの書き込みやniira宛てのDMでもOKです。
————————————————–
Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)
学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。
————————————————–
Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ
https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/
2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓
https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/







