Tipping Point Returns Vol.31 「一読一聴(いちどくいっちょう)」は正しいか?
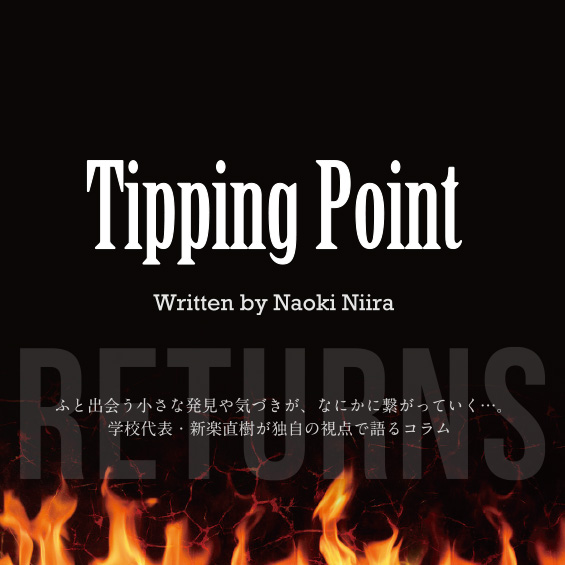
マスメディアから情報を得ようとする場合、読者や視聴者は一度しか読まないし一度しか聴かない――。多少の例外こそあれ、そう考えて言葉を紡ぐのがプロの心得だと伝えてきた。私の授業を受けて、私の顔や名前は思い出せなくても「一読一聴」というフレーズは頭に残っているという人もいるだろう。
日本映像翻訳アカデミーを設立する以前、東京・渋谷にあった編集者やライターの養成校で指導を始めた時からだから、もう30年以上になる。時代は移ろってもこの持論が揺らぐことはなく、「ことばのプロ」を目指す人は強く心得るべしと訴え続けてきた。
今にして思えば、冗談のような話がある。最近の授業では「一読一聴」と説いた瞬間に(なるほどね)、(そういうことか)と受講生の皆さんが納得しているのがわかる。そういう空気だから、すぐに指導を次のステップに進めることができる。ところが、2000年の前半くらいまでは、そうではなかった。「一読一聴」の重要性は、多くの受講生に対して一読一聴では伝わらなかったのだ。
スキルやコツを指導する前に、受講生が自分なりに書いた原稿を「第一稿」と呼んでいる。第一稿から一読に難がある部分を例に挙げて「一読一聴」の有効性を説くのだが、少なからずの受講生が(何それ)、(子供が読む文章じゃあるまいし)などと拒絶反応を示した。拒絶こそせずとも(そうなんだ!)、(知らなかった!)と驚く人がほとんどだった。
「一回だけ読めば言いたいことがすーっと伝わる文章を書くのが正しい行為」ということが、当時の日本社会の常識ではなかったのである。私からそう指摘されて「国語の授業ではそんなふうに教わらなかったのに」と、へそを曲げる受講生がいたほどだ。
しかし、当時もプロの書き手や編集者の世界では、「一読一聴」は口に出すまでもない常識であり、不文律であった。日本人の多くは、自らが読み手のときにはそれを求めるのに、書き手になるとその考え方を否定していた。つまり、読み手と書き手、二つの異なる‛人格’を持ち合わせていたのだ。
今、そんな社会的な矛盾のすべてが解消されたわけではないが、「読み手が負担なく理解できるよう書いたり話したりするのが当たり前」という考え方が広く浸透しつつある。さきほど紹介した「一読一聴」を示された際の受講生の皆さんの反応の変化も、その証拠の一つだろう。学校教育の現場でも「文章というのは読み手が努力して読み解くべきもので、解釈できなかったり誤解したりするのは、読み込みが足りない」などという読解力重視の指導は過去のものになりつつあるという。
表題の「『一読一聴』は正しいか?」という問いに答えるならばこうだ。
正しい。正しいどころかマスメディア上での表現か否かを問わず、あらゆるコミュニケーションの場の常識となりつつある。だからことばのプロは、一心不乱に「一読一聴」の技能を追究し続けなければならないのだ。
昨今、このテーマについて語る、言語研究者や教育者、コミュニケーションの指導者らも増えている。その際は「読み手責任」と「書き手責任」という概念が用いられることが多い。
欧米では古くから書き手の責任、つまり「文章は伝わってなんぼ」という考え方が重んじられてきたのに対し、日本ではなぜか読み手に責任があることを前提とする「読解力育成教育」がなされてきた。だらだらと長いセンテンス、無駄で難解な修辞法、(行間は自分で想像せよ)と上から目線で文脈(コンテキスト)の解釈を押しつける不寛容さ、木を見て森を見ずの構成崩壊文(パラグラフの軽視)……。そんな文章が国語の教科書にまで採用され、理解できないのは読解力が未達のせいだとしてきた。そうした教育を受けていれば、書く文章は自然に読み手責任を前提としたものになる。
しかし、ようやく「読み手責任」VS「書き手責任」の議論に決着がついたようだ。今は読み手に責任を委ねるようでは「ことばのプロ」とは言えない。また、書き手責任を強く意識することで、AIと自身の執筆力の差別化が叶う。「どっちが読者をおもんばかり、寄り添った文章を書けるか。書いた文章に責任を持ち続けられるか。勝負しようぜ!」と。
ことばのプロを目指してる人も、プロとして活動している人も、今一度このことについて考えてみよう。そして、学び取った「一読一聴」の技法を矜持としてほしい。
(了)
今回のコラムで思ったことや感想があれば、ぜひ気軽に教えてください。
☞niiraアットマークjvtacademy.com
※アットマークを@に置き換えてください。
☞JVTAのslackアカウントを持っている方はチャンネルへの書き込みやniira宛てのDMでもOKです。
————————————————–
Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)
学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。
————————————————–
Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ
https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/
2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓
https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/
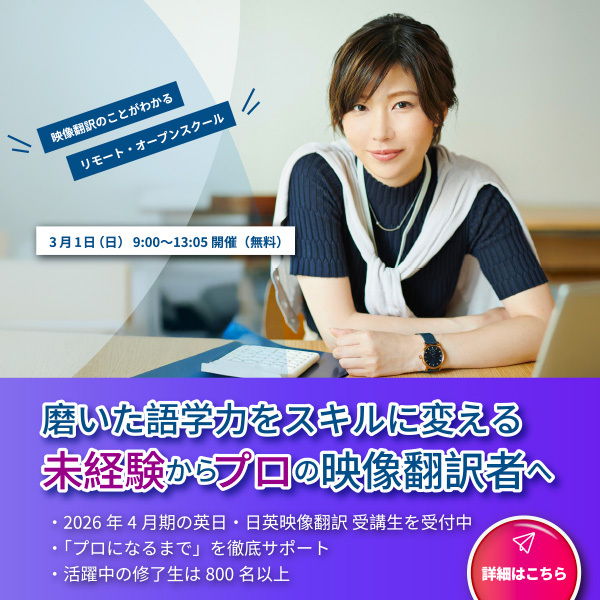
◆【2026年4月期の受講申込を受付中!】
学校説明会を随時開催!
映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。







