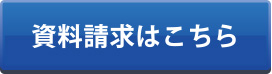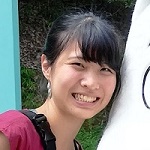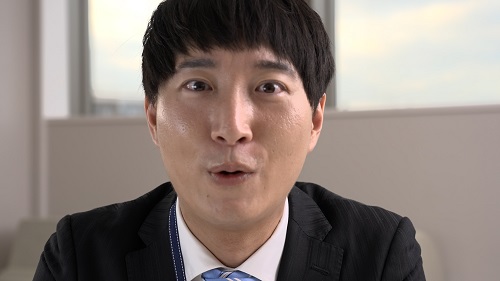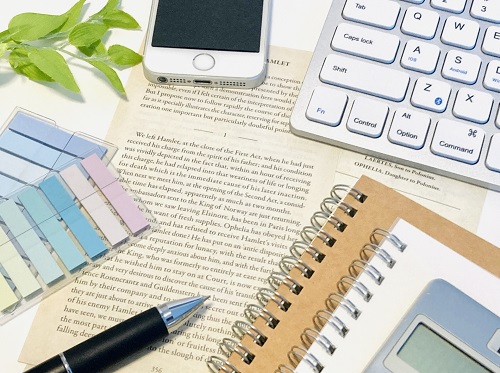【2024年10月期受講生募集】ご興味を持ちの方は「リモート・オープンスクール」へ!7/28(日)開催!
10月第2週より開講! 字幕、吹き替え、多様なジャンルを学べるJVTAで 映像翻訳のプロを目指す! 日本映像翻訳アカデミー(JVTA)は、字幕・吹き替えの翻訳者として活躍するために必要なスキルを学ぶ職業訓練校です。英語から日本語へ翻訳する英日映像翻訳 と日本語から英語へ翻訳する日英映像翻訳 があり、目的に合わせたコースを選んでいただくことができます。コース修了後、当校独自のトライアル(プロ化試験)に合格すれば、併設する翻訳受発注部門よりお仕事を紹介させていただくので、学んだスキルを実践で生かしていただくことができます。プロとして活躍できるスキルを身につけるチャンスです。「リモート・オープンスクール」 にご参加ください。当日は業界ガイド、字幕体験レッスン、スクール説明 を実施。映像翻訳の世界を深く知っていただくことができます。
【こんな方はぜひご参加ください】
英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ(コースの詳細▶こちら 日英映像翻訳 総合コース(コースの詳細▶こちら その他、コースや入学に関するよくあるご質問は▶こちら 会社概要▶こちら
◆ジャパンタイムズの「通訳・翻訳キャリアガイド」のサイト
▶こちら
映像翻訳のすべてが分かる!
オープンスクール 詳細
【日程】すべて日本時間 2024年 7月28日(日)9:00~13:05
▼当日のタイムスケジュール
※映像翻訳のプロとして仕事をする際の目安となる英語力については▶こちら
※タイムスケジュールは変更になることがございます。※入学には「スクール説明」または「リモート個別相談」への参加が必須です。
【参加条件】
【参加形式】
【動画で解説!】現役受講生が答える!受講にまつわる5つの質問
VIDEO
▶JVTAを動画でもっと知りたい方はJVTAの公式YouTubeチャンネル へ
【お問い合わせ】 ▶総合問い合わせフォーム
【ご予約】 フォーム に記入して送信ボタンを押してください。送信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に自動返信メールが届きます。必ずお読みください。
JVTAは情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001:2013」を取得しています。詳しくはこちら
【オープンスクールに参加できない方はこちら】
◆月曜・水曜・金曜に開催!▶「英日字幕体験レッスン」 ▶「日英字幕体験レッスン」 ▶こちらから ▶こちらから
◆割引キャンペーン実施中!
興味を持ったら「リモート留学相談会」へ
◆【映像翻訳にチャレンジしてみたい方におすすめ】 字幕の基礎を学ぶ「映像翻訳講座」
こちら
おすすめ記事・動画 ●【サマスク2022レポート】フリーランス・ブーム到来 「選ばれる職業人」であるために ●【サマスク2022レポート】AIも遠く及ばない “言葉のプロ”の技と業(わざ) ●動画!【字幕翻訳実況】みんなで字幕翻訳実況【Zoom参加者と一緒に考えてみた】#10 ●動画!「現役受講生に聞いた!Why JVTA?」
「JVTAサマースクール 2024」!~1セッションごとに完結 無料講座多数 複数コマの申込も可~
開催期間:2024年7月17日(水)~2024年9月9日(月)
今年もやります!コトバのプロ、目指す人、語学学習者必見の
「JVTAサマースクール 2024」開催!
~1セッションごとに完結 無料講座多数 複数コマの申込も可~
■昨夏はのべ約2,000人が参加!リスキリングのヒントが満載
◆1つから選べる各セミナー
【イベントラインナップ】
◆2024年7月17日(水)19:30 – 20:30 ※日本時間 ※終了しました 映像翻訳者がロサンゼルス留学に踏み切ったワケ~帰国直後の留学生が実体験を語る~
7月に帰国したばかりの元留学生がゲスト!LA留学の最新情報を聞くことができます!
◆2024年7月28日(日)9:00 – 13:05 ※日本時間
映像翻訳の世界がわかる「リモート・オープンスクール」
◆2024年7月30日(火)19:30 – 21:00 ※日本時間
キャリア40年の演出家に聞く!日本語吹き替え版制作のオモテとウラ
誰もが知る劇場公開作品の吹き替え版演出を手掛けてきた演出家に、制作秘話や吹き替え作品の魅力を伺います。
料金:無料
◆2024年8月4日(日)11:00 – 12:00 ※日本時間/8月3日(土)19:00-20:00 ※LA時間
~「好き」を仕事に繋げる留学 第2弾!~ロサンゼルスが教えてくれた私のキャリアパス
◆2024年8月5日(月)19:30-21:00 ※日本時間
「映像翻訳者×AI」の最新事情を公開!~カギは人間の“言語編集力”。「ポストエディット」の真意を理解しよう~
「映像翻訳とAIの関係」を探究する世界でも数少ない専門家が登壇!AIを使った演習パートもあります
◆2024年8月8日(木)10:30 – 11:30 ※日本時間 ~小学生・英語ボランティア体験~ 外国人観光客に道案内&インタビュー
◆2024年8月9日(金)19:30 – 21:00 ※日本時間 難民映画祭のキーパーソンに聞く 増え続ける難民・国内避難民とUNHCRの人道援助活動
「難民」の現状を知り、言葉のプロとして私たちができる支援方法を考えましょう。
◆2024年8月16日(金)YouTubeにて動画配信 翻訳AIの実力を字幕クイズで判定したら「やっぱり人間ってスゴい!」とわかった件
対象者:どなたでも視聴可能
◆2024年8月18日(日)9:00 – 13:05 ※日本時間
映像翻訳の世界がわかる「リモート・オープンスクール」
◆2024年8月21日(水)19:30 – 21:00
劇場公開作品を手掛ける翻訳者が解説~これだけは知っておきたい!吹き替え翻訳の常識~
多くの劇場公開作品を手掛ける吹き替え翻訳者・瀬尾友子氏が再登場!貴重な知っ得情報や裏話が満載です!
◆2024年8月26日(月)19:30 – 20:30 ※日本時間 『ゴジラ-1.0』英語字幕翻訳者に聞く!世界に認められた英語字幕とは?
◆2024年8月29日(木)19:30 – 21:00 ※日本時間 映像翻訳者必見!映画祭作品プログラマーが語る、映画祭の裏側!
「映画祭」という言葉はよく聞くけれど、そもそもどんなものなのか?知られざる映画祭の裏側をご紹介!
◆2024年8月30日(金)19:30 – 21:00 ※日本時間 「クーリエ・ジャポン」流 翻訳上達につながるニュース英語の読み方、訳し方
◆2024年9月1日(日)9:00 – 13:05 ※日本時間 映像翻訳の世界がわかる「リモート・オープンスクール」
◆2024年9月2日(月)19:30 – 20:30 ※日本時間 映画監督と考える! グッとくる日本語字幕ガイド・音声ガイド2
◆2024年9月6日(金)19:30 – 21:00 ※日本時間 フリーランスの新・常識 2024 夏~働き方革命の波に乗れ!完全フリーランスか、兼業・副業か?自分にハマるキャリアパスの選び方
兼業・副業で知っておくべきことや、法令面や顧客対応などにおける事例・留意点などをJVTA代表が解説!
◆2024年9月8日(日)10:30 – 12:00 ※日本時間 「トニー賞」字幕翻訳チーム&米国在住のエンタメ通が深堀り 日本でもファン急増!「ミュージカル翻訳」に注目せよ!
あの歌唱シーンの字幕にはこんな苦労や工夫が!?ミュージカルの裏側をご紹介します!
◆2024年9月9日(月)19:30 – 20:30 ※日本時間 みんなで字幕翻訳~初心者歓迎!あなたのアイディアから名翻訳が生まれるかも?!
人気企画を今年も開催!アイディアを集結し、日本語字幕を完成させよう!
この夏、「コトバのプロ」のための新講座・誕生! ◆2024年7月19日(金)~8月23日(金)19:00 – 21:20 ※日本時間 英語でScreenplay(シナリオ)書いてみよう ~作品理解力を高めて、英語脳を鍛える!~
大手制作会社で数多くの海外動画のローカライズを指揮した経歴をもち、Screenplay(英語脚本)の執筆をライフワークとするクリエーターである高城淳一氏が講師を務める特別講座を開講!
代表からのメッセージ (2024年7月ver.)
JVTAのミッションは、言葉が持つ「社会に伝える力」を最大限発揮し、文化や言語の壁を越え、日本と世界をつなぐお手伝いをすることです。また、その担い手となる言葉のプロフェッショナルを育成することです。
「言葉のプロフェッショナル」を目指す人と出会い、共に学び、共に育つ
JVTAのプロフェッショナルな「言葉づくり」の土台を支えるのが、職業訓練校「日本映像翻訳アカデミー」の運営です。2026年に東京校は開校30周年を迎えます。2008年に開校したロサンゼルス校は、米国カリフォルニア州教育局より正規の学校として認可を受け、留学生(M-1ビザ)を迎え入れることができる職業訓練校です。「動画の時代」への変化を予測し、字幕・吹き替え翻訳の最新技能を指導すると共に、我が国ではそれまで曖昧であった「映像翻訳技能の理論」を明文化して社会に広める努力を重ねてきました。
技能習得者を実業に導くまでが、私たちの役割
私たちと共に学び、力をつけた方々を実業の世界への導くのも当校の重要な役割です。フリーランス一本であれ、兼業でのスタートであれ、修了生を実業へのデビューへと切れ目なく導く仕組みを東京とロサンゼルスに構築。受講生・修了生にこうしたロードマップを示せることも、大きな強みです。「JVTAはコースを修了してからが本番だ」。修了生からそんな声が聴こえてくると、サポート体制のさらなる充実に向けての意欲が生まれます。
Naoki Niira
【染野日名子さんインタビュー】翻訳者としてキャリアを共に重ねてきた「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」への想い
7月13日、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭が開幕、串田壮史監督の『初級演技レッスン』のオープニング上映後、関係者によるオープニングパーティが行われた。JVTAは今年も同映画祭の上映作品10作品の英語字幕を担当。翻訳者の染野日名子さんとJVTAスタッフが参加してきた。
染野さんは今年、『 初級演技レッスン』のチーム翻訳に参加したほか、これまでも同映画祭に数多く携わってきた。翻訳者として初めて関わったのは、2018年。翻訳ディレクターの指導を受けながらゼミ形式で字幕制作を行う『英語字幕PROゼミ』に参加し、短編作品『はりこみ』(板垣雄亮監督)の字幕を手がけた。その後、2021年に『親子の河』(望月葉子監督)、2022年に『明ける夜に』(堀内友貴監督)などを手がけたほか、2021年以降は、JVTAが字幕を担当した全作品のチェックとスタジオ収録に立ち会うなど、現在ではJVTAのディレクターたちも厚い信頼を寄せる存在となっている。映画やドラマ、アニメ、歌詞対訳、企業のプレスリリースなど幅広いジャンルで活動中だ。
『初級演技レッスン』©2024 埼玉県/SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ 『初級演技レッスン』は、廃工場で行う即興演技を通じて人々の記憶に侵入する男が、夢と現実の狭間で《奇跡》に出会うという物語だ。染野さんはこの日、ワールド・プレミアとなったオープニング上映にチームとして共に翻訳を手掛けたサンディ・ファンさんと谷山優果さんと駆けつけた。上映前の舞台挨拶には、串田壮史監督と出演の毎熊克哉さん、大西礼芳さん、岩田奏さんが登壇。作品の関係者と観客と共に鑑賞し、その反応を肌で感じることができたという。
左からの毎熊克哉さん、大西礼芳さん、岩田奏さん、串田壮史監督 「串田壮史監督は、字幕のスタジオ収録にも立ち会ってくださり、英語の細かいニュアンスを話しあえたのも貴重な経験でした。スクリーンのエンドロールに翻訳者として3人の名前が流れた時は感動しました。来賓のゲストの皆さんが『難しい作品だった』と話されていましたが、翻訳時にはチームみんなで時系列に並べ替えたり、解釈を話し合ったりしたのがとても楽しかったです。」(染野さん)
串田監督は、2020年に長編デビュー作『写真の女』で同映画祭SKIPシティアワードを受賞した後、デッドセンター映画祭(米)の長編グランプリをはじめ、世界中の映画祭で40冠を達成し、7カ国でリリースが決定。そして昨年も『マイマザーズアイズ』が2作品連続でSKIPシティの国際コンペティションにノミネートされ、トリエステ国際SF映画祭(イタリア)など多くの映画祭に正式出品されるなど世界で注目を集めている。これまでアメリカ、イギリス、プエルトリコなどの映画祭に参加してきたという串田監督に、オープニングパーティで英語字幕に関する想いを伺った。
串田壮史監督と染野日名子さん JVTAのディレクターと 「英語字幕はネイティブだけが観るわけではないので、できるだけ簡潔な英語がいいと思います。例えば、同じ英語字幕で上映する場合もアメリカの映画祭とドイツの映画祭では観客は全く違うはずです。映画祭は世界の見本市で、英語で世界中に売るのですが、国によっては現地の人がそれを基に現地の言葉に訳しますし、アメリカなどで上映の場合はもっとネイティブ寄りの英語に直すこともあります。ですから、始めの段階では、英語があまり得意ではない人にも分かる字幕がいいと思いますね。」(串田壮史監督)
染野さんが収録スタジオで串田監督と話し合ったのは、主人公の男性が演技レッスンをする廃工場にかけてある時計に関する彼のセリフだという。
「時計は、止まったままにしてあります 時間を気にすると演技に集中できないので」
「はじめは“I’ve stopped the clock”となっていたのですが、私の意図としては彼が時計を止めたのではなく、始めから止まっていたというニュアンスでした。それがこの廃工場のキャラクターでもあり、彼がこの場所を選んだ理由でもあります。そこで、最終的には“I’ve left the clock stopped”にしていただきました。」(串田監督)
世界の映画祭での上映を数多く経験されている串田監督ならではの言葉は、私たち映像翻訳者にとって改めて英語字幕の役割や方向性を考える機会となった。
今年担当した10作品の中でも、染野さんが個人的にとても好きだという短編『だんご』の田口智也監督にも会場でお会いすることができた。この作品は俳優として活動する田口さんの初監督作品で自ら主人公を演じている。出所した兄と迎えに来た弟が生き別れた妹を探す旅に出るが、道中財布をなくした女性と出会う…という物語だ。田口監督によると、セリフはアドリブも多かったのだという。「グリコで遊んでいて階段から落ちた」「縁結びの神社やお守り」など日本ならではの文化が盛り込まれたセリフの訳し方や、「えっ」「え~」と兄弟で同じようなセリフを連発するシーンでは意味をくみ取りながら訳し分けをしたといった翻訳時のエピソードをお話しすると、撮影で実際に小道具として使ったというお守りを見せてくださった。こちらもテロップとして解説を入れたと伝えると「確かに英語では分からない設定も多かったですよね、ありがとうございました。」と大きく頷いていた。
『だんご』©2024 Yoshitaka Tateishi
「僕は全く英語を話せないので、自分の作品に英語字幕を付けていただけることを、実は密かに楽しみにしていました。アドリブのシーンも多くて、台本に書かれたセリフではないので、そのシーンのノリや空気感とかも重要だったりすると思うのですが、オープニングパーティーで染野さんやJVTAのみなさんとお話をさせていただいた時に、そういった部分も大切にしてくださっていたこと、作品の世界観をそのままに、言葉1つ1つ丁寧に、色々工夫して、より伝わりやすく翻訳してくださっていたことをお聞きして大変感激しました。当日、英語字幕が付いた自分の作品を観られてとても嬉しかったです。ありがとうございました!」(田口監督)
田口智也監督と染野日名子さん JVTAディレクターと
「田口監督とお兄さん役の沖田修一さんのファンということもあり、ほのぼのとした雰囲気の中に笑いの要素がたくさん散りばめられていて、とても好きな作品です。田口監督にエンディングの疑問についてお尋ねしたところ、丁寧に教えてくださいました。」(染野さん)
SKIPシティ国際Dシネマ映画祭では、コンペティション部門の応募資格は、長編映画制作数が3本以下の監督の作品と定められており、今回が初監督作品というケースも多い。短編部門のアニメ『チューリップちゃん』の渡辺咲樹監督もその一人だ。主人公は、小学生の女の子チューリップちゃん。将来の夢は「還暦を孫にお祝いしてもらうこと」と語り、周囲に馴染めない彼女の成長をシュールなタッチで描いている。東北芸術工科大学映像学科卒業制作として手がけたこの作品では、監督・脚本・作画・音楽を渡辺監督が一人で務めている。エンディング曲の作詞作曲も手がけたという。
『チューリップちゃん』©sakichi
翻訳チームが字幕で迷ったのは、チューリップちゃんの独特なセリフの数々だ。進路指導の教師とのやり取りでは、「明けない夜はない」と言われれば「暮れない昼もない」と返し、「そうやってふざけてばかりいると食べていけなくなるぞ」と諭されれば「食べていけなくなったら、ドリンクバーに行って飲み物を飲みます」と返す。前後の流れの面白さを残しながら意味をきちんと伝えるために、翻訳者たちは苦労したという。「食べていく」とは生活をしていく(make a living)の意味だが、その解釈をいれるとドリンクバーとの対比が消えてしまう。結果的には、put food on the table(養う)という表現を使ってドリンクバーに繋がるセリフにしたという。英語字幕はただ、訳すだけではなく、全体の流れを作ることも重要なのだ。
渡辺咲樹監督と染野日名子さん、JVTAディレクターと
「この作品のセリフは一筋縄ではいかないものばかりで、通訳をしている母からも英語字幕は無理なんじゃない?と言われていました。皆さんがそんな風に考えて作ってくださったと伺い、感激しています。私は英語の細かいニュアンスまでは分からないのですが、一緒に鑑賞予定の母にじっくり見てほしいと思います。」(渡辺咲樹監督)
会場では、ある関係者が染野さんに声をかけてくる場面も。聞けば、2022年の上映作品の撮影担当の方で、映画の公式Xを染野さんがフォローしたことから繋がったそうだが、直接お会いしたのは、この日が初めてだという。映画関係者と直接交流できるというのも映画祭の醍醐味だ。
「昨年私が一番気に入った作品の監督さん(永里健太朗さん)とは、パーティーや上映後にお話させていただき、その後Xでもつながらせていただきました。作品もご本人もとても面白い方で、今後のご活躍をとても楽しみにしています。今日は、『初級演技レッスン』主演の毎熊克哉さんともお話しすることができました。会場でお会いした監督の皆さんから、英語字幕に寄せる期待と海外出品への意欲を伺えたことも励みになりました。また、原稿のチェックや収録に立ち会うことで多くの翻訳者さんとの交流からも刺激をもらっています。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭からは翻訳者としてこれまで多くを学ばせていただきました。」(染野さん)
今年からは日英翻訳に加え、英日映像翻訳者としての活動も開始した染野さん。フリーランスとして積極的に繋がる行動力を駆使して今後ますますキャリアを広げていくに違いない。
◆SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2024(第21回)
《スクリーン上映》2024年7月13日(土)~ 7月21日(日)
《オンライン配信》2024年7月20日(土)10:00 ~ 7月24日(水)23:00
公式サイト:https://www.skipcity-dcf.jp/
【関連記事】
◆SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2024が7月13日開幕 審査委員長は白石和彌監督と横浜聡子監督
◆SKIPシティ国際Dシネマ映画祭×JVTA 10年に及ぶ英語字幕PROゼミがもたらしたもの
◆【次期開講は2024年10月】 英日・日英映像翻訳にご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら
◆割引キャンペーン実施中!
興味を持ったら「リモート留学相談会」へ
【2024年7月】英日OJT修了生を紹介します
JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。さまざまなバックグラウンドを持つ多彩な人材が集結。映像翻訳のスキルを学んだことで、それぞれの経験を生かしたキャリアチェンジを実現してきました。今回はOJTを終え、英日の映像翻訳者としてデビューする修了生の皆さんをご紹介します。
◆青井夕子さん(英日映像翻訳実践コース修了)
職歴:医療機器メーカーの品質保証部にて監査業務を担当
【今後どんな作品を手がけたい?】
高校時代にスキューバダイビングを始め、大学時代はハワイとアラスカで動物科学を学びながら、イルカの研究所で働いたりクジラウォッチングツアーのガイドをしたりしました。動物の知能や社会的行動に興味があり、最近はタコに惹かれています。動物ドキュメンタリー番組が大好きですが、まずはどんなお仕事にも挑戦し、様々な知識やテクニックを身につけたいと思っています。
【JVTAを選んだ理由、JVTAの思い出】
複数の説明会に参加しましたが、キラキラと活気に満ちた雰囲気が伝わってきたのがJVTAでした。講義では、講師の方々の翻訳に対する情熱に感動させられっぱなしでした。このような環境で学べることのありがたさ、楽しさに気づき、息子や娘の100倍は勉強したと思います。また1年半、共に学んだクラスメートは、私にとって生涯の友と呼べる大切な存在となりました。
◆長谷舞さん(映像翻訳Web講座 プロフェッショナルコース修了)
職歴:メーカーの海外窓口業務→特許翻訳・チェック(日英、独日)
【映像翻訳を学ぶきっかけ/JVTAを選んだ理由】
駐在帯同でアメリカへ引っ越し、帰国後のキャリアについて考えていた時、前職の翻訳が頭に浮かびました。調べていく中で見つけた「映像翻訳」という仕事は、自分の経験を生かしながら、育児と両立してできそうだと思いました。JVTAには、海外にいても課題の添削を受けられる映像翻訳Web講座があったことから(※当時)、受講を決めました。
※現在、映像翻訳Web講座は日本国内のみの受講です。
【今後の目標】
英日の映像翻訳には、文字数の制限の他にもたくさんの約束事があり、大変難しい仕事だと感じます。受講中、心が折れそうになる夜もありました。それでも、プロになった以上は諦めずに言葉にこだわり抜き、作品に込められた意図をより良く伝えられる翻訳者を目指します。また、第二の故郷であるドイツで身につけたドイツ語も役立てていきたいです。
◆林友理恵さん(英日映像翻訳実践コース修了)
職歴:旅行会社(手配・仕入れ担当)⇒3DCG制作スタジオ(通翻訳担当)
【JVTAを選んだ理由、JVTAの思い出】
先輩にJVTAを紹介してもらったのがきっかけです。毎週課題をこなすのは大変でしたが、同じくらい楽しかったです。良い訳文が出てこない時は一度寝かせていたのですが、シャワーを浴びている時や、眠る直前にパッとひらめくことがありました。そういう時は浴室や寝室から飛び出して、メモ帳に走り書きしたのも良い思い出です。
【今後どんな作品を手がけたい?】
旅行会社に勤めていた経験を生かして、世界各地の文化を紹介できるような作品に携わりたいです。特に、食べることが大好きなので、世界のいろいろな料理や食文化を紹介する作品を手掛けてみたいです。また、現在3DCG制作スタジオで通翻訳の仕事をしているので、いつか長編アニメ映画の翻訳を手掛けるのも目標の一つです!
◆松本有紀子さん (英日映像翻訳 実践コース修了)
職歴:コピーライター職、外資メーカーのローカライズ担当
【JVTAを選んだ理由、JVTAの思い出】
良質の授業と手厚いフォローが選んだ理由です。実は他社で数件お仕事を経験しましたが、作業中に不測の事態が生じると常に手探り状態でした。そこでJVTAへの編入を決意。授業での解説には、実務で起こりがちな問題や「こんな時どうする?」という疑問が全て網羅されていました。JVTAでしっかり学び実践に生かせば、どんな案件でも自信をもって対応できると実感しています。
【今後どんな作品を手がけたい?】
コメディです。海外のジョークやダジャレは文化も違うため直訳だと伝わりにくく、原文から逸脱せずに面白さを伝えるのが難しくもありますが、ぜひ挑戦したいです。VRやPCゲームも好きで、ゲームが原作の作品にも興味があります。また70‐90年代の洋楽で育ち身近な分野のため、音楽関連の作品も手がけたいです。国際問題にも興味関心がありますが、何でも幅広く挑戦したいです。
OJT修了時に同じチームの皆さんの食事会での1枚。 翻訳仲間との繋がりは大切にしたいですね。
★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!
◆翻訳の発注はこちら
◆OJT修了生 紹介記事のアーカイブはこちら
◆【次期開講は2024年10月】 英日・日英映像翻訳にご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら
◆割引キャンペーン実施中!
興味を持ったら「リモート留学相談会」へ
【サマースクール2024】~「好き」を仕事に繋げる留学 第2弾!~ロサンゼルスが教えてくれた私のキャリアパス
【JVTAサマースクール2024】 JVTAが毎夏開催するオンラインセミナーシリーズ!
2024年8月4日(日)11:00-12:00 ※日本時間
留学を経験した、英日・日英の映像翻訳者が登壇!
【こんな方におススメ!】
【内容】
【登壇者】
中村早希さん(英日・日英翻訳者)
日程:2024年8月4日(日)11:00~12:00 ※日本時間
参加費:無料
◆JVTAオンラインサマースクール2024◆▶こちら
◆割引キャンペーン実施中!
興味を持ったら「リモート留学相談会」へ
【サマースクール2024】キャリア40年の演出家に聞く!日本語吹き替え版制作のオモテとウラ
【JVTAサマースクール2024】 JVTAが毎夏開催するオンラインセミナーシリーズ!
2024年7月30日(火)19:30-21:00 ※日本時間
ベテラン演出家の視点で吹き替え制作の現場に迫る!
今回は約40年にわたり様々な作品の吹き替え版制作を手掛けてきた吉田啓介氏をゲストに迎え、プロダクション=作品制作の視点から吹き替えコンテンツの魅力を紐解いていきます。よい吹き替え作品とは何か?その面白さの源はどこにあるのか?これまで演出した作品の制作エピソードや映像のローカライズの難しさ、スタジオ作業の流れなどについて吉田氏に詳しいお話を伺いながら探っていきます。また営業、制作進行、翻訳チェック、演出と制作のほぼ全工程に関わってきた吉田氏のキャリアパスにも注目。映像業界の第一線で活躍する職業人としての仕事術についても掘り下げます。
【こんな方におススメ!】
【内容】
【登壇者】
吉田啓介氏(吹き替えディレクター)
【進行役】
石井清猛(JVTA) Media Translation and Accessibility Lab(翻訳室)リーダー。
日程:2024年7月30日(火)19:30~21:00 ※日本時間
参加費:無料
◆JVTAオンラインサマースクール2024◆▶こちら
想像と対話から始まる「すべての人にやさしい世界」への第一歩「WATCH 2024」上映イベント開催レポート
「障害者差別解消法」により、2024 年4月から民間業者にも合理的配慮の提供が義務化された。合理的配慮とは、障害の有無に関係なく、すべての人々が平等に社会生活を送れるようにするために日常生活に存在する様々な障壁を取り除くための措置である。しかし一口に「障壁を取り除く」と言っても、実際にどのようなアクションを起こせばいいのか?WATCH 2024 」『こころの通訳者たち What a Wonderful World』予告編
VIDEO
インターン生と舞台手話通訳に関する有識者が対談 。「舞台手話通訳と映像翻訳は似ている」 様々なケースを想像し、できることから取り組むことがやさしさの第一歩
◆WATCH 2024: For a Sustainable Future公式サイトは ▶コチラ
最後は企画担当者と萩原さんで記念写真!
関連記事:社会をより良くする方法を大学生と考えませんか?WATCH 2024にて、上映会+トークイベントを開催します! 国内外の大学生インターンと共に作り上げる無料オンラインイベント「WATCH 2024: For a Sustainable Future」の進捗をレポート
◆【次期開講は2024年10月】 英日・日英映像翻訳にご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら
◆割引キャンペーン実施中!
興味を持ったら「リモート留学相談会」へ
【JVTAが英語字幕】多重婚を描いた短編映画『♡≠2』が韓国の映画祭で脚本賞を受賞
日本の学生が制作を手がけた短編映画『♡≠2』(Love not equal Two)が韓国のIncheon International Short Film Festivalで、BEST SCREENPLAYを受賞した。この作品は上條 凜斗監督が日本工学院専門学校 放送芸術科の卒業制作として発表したもので、多重婚がテーマとなっている。
英語字幕を担当したのは、JVTAで学んだ日英映像翻訳者の三宅マーディさんだ。三宅さんは、これまで映画、ショートフィルム、ドキュメンタリー、脚本、漫画、企業PRの日英翻訳に加え、字幕のチェック、英語の聞き起こしなど幅広いジャンルで活躍している。
『♡≠2』では多重婚をしている主人公の太郎の日常が描かれ、字幕は主に職場の同僚や家族との会話だ。一方、冒頭には少し堅い表現で多重婚が認められた社会についての解説もあり、英語でもトーンの使い分けが求められる。
『♡≠2』(Love not equal Two)
「斬新なテーマの中で描かれている人間関係が面白いと思います。日常会話の台詞が多かったのでそれに合わせてカジュアルかつ自然な言い回しを使うように心がけました。『そうですね』『そう?」』『どうしたんですか』『大丈夫』など短い台詞が映画の中に繰り返されましたが、自然な流れの中でできるだけいろいろなフレーズを考えて表すようにしました。」(三宅マーディさん)
日英の翻訳において、実は日常の何気ない会話の訳出が意外と難しい。主語がなくても成り立つ日本語は短く断片的だが、英語にすると長くなりがちであると同時に、前後の流れによっては同じ言葉でも話者の意図が変わることもある。例えば「おいしい」という言葉も“delicious” “tasty””good“ “yum”などを使い分け、「ごちそうさま」も“Thanks for dinner”や“I’m full”など人物の表情やお皿の料理の状態を考慮して表現を変えるなどの工夫もされている。また、「ほ、ほんとうに」というセリフでは“R…really? ”と同じニュアンスを盛り込み、自分に言い聞かせるように「大丈夫」「大丈夫だよ」と繰り返す場面では“It’s okay” “It’ll be okay”といった微妙な表現で訳し分けた。
日英映像翻訳ではこうした日常会話を訳す際、映像のトーンと合っていなかったり、堅すぎる印象だったりすると、ネイティブには違和感がある。いかに自然な流れで字幕を意識させずに作品全体を楽しめるかが鍵となる。それだけに今回、言葉に贈られた国際映画祭での脚本賞受賞は翻訳者にとっても嬉しいニュースとなった。
「この作品がIncheon International Short Film Festivalにて脚本賞を受賞したことを聞いてとても嬉しかったです。こんな素敵な作品に関われたことをとても光栄に思っています。脚本を手がけた上条凛斗監督のこれからのご活躍を応援しています。」(三宅マーディさん)
上條 凜斗監督、関係者の皆さん、おめでとうございます。
今後、また英語字幕付きで他の映画祭での上映をぜひ期待しています。
※この作品は日本工学院の公式サイトで見ることができる。(英語字幕はなし)
https://www.neec.ac.jp/exhibition/2024/creators/kamata_screen/work002.html
◆【次期開講は2024年10月】 英日・日英映像翻訳にご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら
◆割引キャンペーン実施中!
興味を持ったら「リモート留学相談会」へ
SKIPシティ国際Dシネマ映画祭×JVTA 10年に及ぶ英語字幕PROゼミがもたらしたもの
映像クリエイターの登竜門として知られる「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」が今年も7月13日(土)に開幕する。この映画祭は、“新たな才能を発掘し、育てる映画祭へ”をモットーに、これまで白石和彌監督(『孤狼の血』『碁盤斬り』)、中野量太監督(『湯を沸かすほどの熱い愛』『浅田家!』)、石川慶監督(『愚行録』『ある男』)、上田慎一郎監督(『カメラを止めるな!』『スペシャルアクターズ』)など国内外の多くのクリエイターを生み出してきた。
JVTAは、主にこの映画祭の国内コンペティションにノミネートされた作品の英語字幕を手がけている。特筆すべきは、2013年から約10年、この映画祭とタッグを組んで毎年「英語字幕PROゼミ」を継続的に開催していることだ。「英語字幕PROゼミ」では、翻訳者がゼミ形式で字幕を制作し、プロの映像翻訳ディレクターのフィードバッグを受けて、最終的な字幕を作成する。アメリカ出身のジェシー・ナスディレクターは、このゼミの開始当時から指導にあたってきた。JVTAで多くの日英翻訳案件に携わり、日本人監督が海外の映画祭に出品する際のサポートなどの経験も豊富だ。自身も『不気味なものの肌に触れる』(濱口竜介監督)の英語字幕を手がけたほか、『笑顔の向こうに』(榎本二郎監督)が第16回モナコ国際映画祭で最優秀作品賞を受賞した(関連記事はこちら )際の英語字幕のチェックや出品に関するサポート(現地とのメール対応や出品の手続き)などを行ってきた。
ジェシー・ナス ディレクター
「『英語字幕PROゼミ』の大きな特徴は2~4人のチームで翻訳し、出来上がった字幕が、同映画祭で上映されることにあります。ゼミの中では、細かい表現について徹底的に考えていきます。決して間違いではないけれども、ネイティブが見ると不自然に思えるワードチョイスや、話者の心情を深くくみ取ったニュアンスが反映されていないと思う語句などについて、より的確に伝えるためのヒントを考察します。とはいえ、視聴者はネイティブだけではありませんし、英語字幕は今後、これを基に多言語に翻訳される可能性もありますので、どんな人が見ても分かる英語にする配慮も必要です。実際、私たちが多言語の作品を日本語に訳す時もオリジナルの原語ではなく、英語字幕から訳すケースが多いという現状があります。指導側の立場として大切にしているのは、こちらからすぐに代案を出すのではなく、2度にわたる細かいフィードバックを受けてチーム内でリライトすること。実際の翻訳の仕事では納期までの時間も短く、学びながら時間をかけて自らブラッシュアップできるケースは稀であり、翻訳者にとっても大きな学びになります。」(ジェシー・ナス ディレクター)
イメージ ジェシーディレクターによると、新人翻訳者にとって特に難しいのは自然な日常会話の流れを作ることと作品の解釈(シーンの意味や作品のテーマ)だという。さらにセリフの量や全体の内容など考慮して作品を選んでいる。翻訳者にとっては、出来上がった英語字幕を映画祭のスクリーンで観られる(字幕制作者のクレジットを表示)のも嬉しいポイントだ。
「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭では上映後にトークショーが行われ、監督や出演者が登壇することもあります。翻訳者が会場に足を運べば、直接、制作者と交流できるチェンスがあるのも映画祭ならではですし、これは日本の作品に携わる日英翻訳ならではの醍醐味とも言えます。」(ジェシー・ナス ディレクター)
「英語字幕PROゼミ」ではこれまで、『カメラを止めるな!』の上田慎一郎監督、『湯を沸かすほどの熱い愛』の中野量太監督など今注目を集める監督たちが過去に手がけた短編映画の英語字幕も手がけてきた。翻訳者にとってまさに未来のクリエイターの傑作に出合える素晴らしい機会となっている。一方、初期のPROゼミに当時新人として参加した翻訳者たちも経験を重ね、今では講師やディレクターとして新人翻訳者の指導にあたったり、ヴェネチア国際映画祭 銀獅子賞(監督賞)を受賞した『スパイの妻』(黒沢清監督)の英語字幕(関連記事はこちら )を手がけたりするなど、この10年で大きな実績を残している。学びと実績を兼ね備えたこのゼミに参加したいという希望者は多く、今では募集後すぐに満席になる人気を集める講座の一つになった。国際映画祭出品で英語字幕がつくことは、映画制作側にも海外を視野に入れる大きなチャンスとなる。ぜひ、英語字幕にも注目しながら鑑賞してほしい。
◆SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2024(第21回)
《スクリーン上映》2024年7月13日(土)~ 7月21日(日)
《オンライン配信》2024年7月20日(土)10:00 ~ 7月24日(水)23:00
公式サイト:https://www.skipcity-dcf.jp/
【関連記事】
◆SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2024が7月13日開幕 審査委員長は白石和彌監督と横浜聡子監督
◆【染野日名子さんインタビュー】翻訳者としてキャリアを共に重ねてきた「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」への想い
◆【次期開講は2024年10月】 英日・日英映像翻訳にご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら
◆割引キャンペーン実施中!
興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

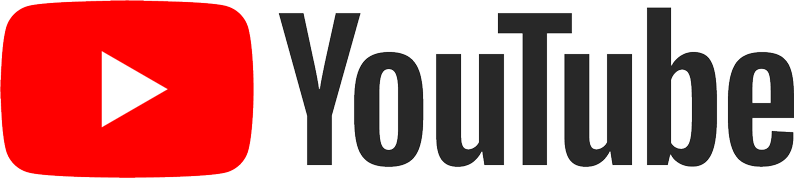
![]()